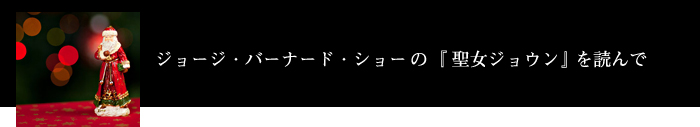
アイルランドの劇作家・作家・批評家のバーナード・ショウをご存知ですか?
プロフィールをご紹介すると、1856年ダブリンで下級貴族の穀物商人の子として生まれ、
貧困のため小学校を卒業後は独学し、20歳でロンドンに出て演劇や音楽などの評論に携わった後、1892年『やもめの家』で劇作家としてデビュー。辛辣な風刺と機知に富んだ表現で劇作家として活躍し、イギリス近代劇の創始者と称されました。
そして、1923年の作品『聖女ジョウン』(または『聖女ジャンヌ・ダルク』) はそれまで悲劇のヒロインとして描かれてきたジャンヌ・ダルクを、社会と葛藤する一人の人間として描き、1925年にノーベル文学賞を受賞しました。
ジョウンは、「神の声」を聞くことができました。そして、その「声」に忠実に行動し、周囲の人間を動かし、イギリスの包囲からオルレアンを解放します。
しかし、「神の声」を聞くことができるジョウンに対して、教会関係者は恐れを抱きます。やがて異端とみなされてしまった彼女は、宗教裁判にかけられ、焚刑に処せられてしまいます。
なぜ、ジョウンは死ななければならなかったのだろうか。私は、『聖女ジョウン』を読んで、その点について考えました。
ジョウンは「神の声」を聞いて、その声に忠実に行動した。だからこそ、イギリスの包囲からオルレアンを解放することができたのです。
しかし、ジョウンの聞いた「神の声」は(当時の)教会の教えとは異なっていました。ジョウンの聞いた「神の声」が真実のものであるとするならば、それと異なることを伝える教会の存在意義は失われてしまいます。だからこそ、教会は彼女を異端として扱わなければなりませんでした。
自分に都合の悪い存在を抹消したいという社会の不寛容さゆえに彼女は死ななければならなかったのです。
バーナード・ショウの描いた『聖女ジョウン』は、エピローグがあり、彼女の焚刑に関与した人々は、自分の行動を振り返り、反省を迫られるのシーンがあります。
私はこの作品を読み終えて、そうした反省の結果、今のキリスト教会があるのではないだろうかと思いました。ジョウンは、教会が本来の姿を取り戻す契機を作るために、死を受容したのではないかと思ってしまう。
かつては、信仰を全うするために死を選択しなければならない時代もあったのかもしれません。しかし、今、私たちは、好きなときに聖書を読み、好きなように聖書についての議論ができる。それは、まさにジョウンを始めとする信仰の先駆者のおかげであると思う一冊でした。
Merryy Christmas
クリスマスは、街もとても楽しい空気であふれていて、普段何気なく教会に通っている私も、毎年,神様との関係を振り返ってみようと思っています。今年は、『聖女ジョウン』を通して、いかに自分が自由で幸せに信仰生活を送れているかを実感することができました。 こんなに素敵な世界を創造してくださり、私の救いのためにイエス様までお遣わしなってくださった神様に感謝して、アドベントの日々を充実させていきたいです。
★Next (詳しいメニューは左メニューからご自由にお選びください。)